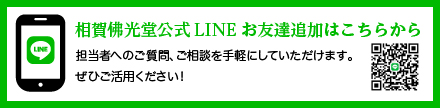一周忌・三回忌・七回忌ってどう違う?
皆さまこんにちは。玉野で仏事のお手伝いをして40年以上、相賀佛光堂です。よくある葬儀・葬式・法要のマナーの心配ごと、今回のテーマは「一周忌・三回忌・七回忌の違い」についてご紹介します。
日本では古くから、亡くなった方を供養するための「年忌法要(ねんきほうよう)」が行われてきました。法事とは「故人を偲び、感謝を伝える時間」です。その中でも特に重要とされるのが「一周忌」「三回忌」「七回忌」です。しかし、名称だけではその違いや意味、マナーが分かりづらいという方も多いのではないでしょうか?
この記事では、それぞれの法要の意味やタイミング、マナーについて分かりやすく解説します。
一周忌(いっしゅうき)とは?
意味:故人が亡くなってちょうど満1年目の命日に行う法要
特徴:喪が明けて初めての大きな節目とされ、親族だけでなく友人・知人も招くことが多い
準備すること:
・ 僧侶の読経依頼
・ 法要後の会食(仕出しや会場予約)
・ 引き出物(返礼品)の準備
服装:正喪服または準喪服(黒系のフォーマル)
三回忌(さんかいき)とは?
意味:亡くなった年を「一回目」と数えるため、実際には命日から満2年後に行います
特徴:一周忌よりは規模を縮小し、親族中心で行われることが一般的
注意点:数え年で行うため、計算ミスに注意しましょう
準備すること:
・ 法要後の会食(仕出しや会場予約)
・ 引き出物(返礼品)の準備
七回忌(しちかいき)とは?
意味:故人が亡くなって満6年後に行う年忌法要
特徴:遺族だけで行う場合も多く、だんだんと身内中心の行事になっていきます
マナーのポイント:
・ 家族だけの場合でも、仏壇やお墓へのお参りは丁寧に
・ 供物やお線香は、仏式に合ったものを選ぶ
他の年忌法要との違いは?
「一周忌」「三回忌」「七回忌」は、故人が亡くなってから比較的近い年数で行われるため、特に重要な節目として広く行われます。これに対して、十三回忌以降の年忌法要(十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌など)は、節目の供養としての意味合いが強まり、遺族中心で簡略に行われる傾向があります。
「一周忌〜七回忌」は親族や知人を招いて行うことが多いのに対し、十三回忌以降は家族のみ、または内輪で静かに行われることが多くなるのが一般的な違いです。
法要で気をつけたいマナー
・ 香典の金額:3,000円〜10,000円(関係性による)
・ 服装:フォーマルな黒系の服装。夏でも露出は控えめに
・ 遅刻は厳禁:読経開始の15〜30分前には到着しておくのがマナーです。
まとめ|思いを伝える、心を整える法要の時間
法要は形式的に行うものではなく、「故人を偲び、今ある命に感謝する」大切な時間です。家族や親族が集まり、静かに故人を想う時間を持つことは、残された私たちの心を整えるきっかけにもなります。年忌法要を通じて、感謝や祈りの心をつなげていきましょう。
また、法要やご葬儀に関してわからないことがある方や、準備が難しい方は相賀佛光堂にご相談ください。相賀佛光堂は、玉野市・岡山市南区エリア(旧灘崎町、迫川、荘内、常山、八浜、宇野、築港、直島、豊島)で「地元とともに生きる」葬儀社です。地元で安心して葬儀をあげていただけるよう、まごころを込めてお客様に寄り添いサポートいたします。仏事でお困りの際はお気軽にご相談ください。