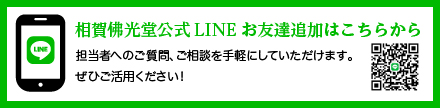家族葬のあとどうする?お別れ後の初盆・法要の流れと準備ガイド
皆さまこんにちは。玉野で仏事のお手伝いをして40年以上、相賀佛光堂です。よくある葬儀・葬式・法要のマナーの心配ごと、今回のテーマは「家族葬のあとの供養の流れ」についてご紹介します。
近年、家族葬を選ぶご家庭も増えています。小規模であたたかいお別れができる一方で、葬儀後の流れについて「何をすればいいのかわからない」と感じる方も少なくありません。
特に、初盆や法要など、故人を偲ぶ供養はどうすればよいのか悩む声が多く聞かれます。家族葬のあとの供養の流れや、初盆・法要の準備についてわかりやすく解説します。
1. 家族葬後に行う主な供養とは?
家族葬を終えたあとも、仏教の習わしでは故人の魂を偲び供養する行事が続きます。主に以下のような供養があります。
・ 初七日法要(最近は葬儀と同日に行うことが多い)
・ 四十九日法要(忌明けの大切な節目)
・ 一周忌・三回忌法要(年ごとの供養)
・ 初盆(新盆)(亡くなって初めて迎えるお盆)
家族葬は形式を簡略にしたお別れですが、供養自体を省略してよいという意味ではありません。ご家族の中で話し合い、必要な供養を無理のない範囲で行っていくことが大切です。
2. 初盆(新盆)とは?流れと準備
初盆とは、故人が亡くなってから初めて迎えるお盆(一般的には8月13〜16日)のことをいいます。特に初めての年は「新盆」と呼ばれ、通常のお盆より丁寧に供養する風習があります。
【準備しておきたいこと】
・ お寺への依頼(読経をお願いする場合)
・ 精霊棚の準備(仏壇とは別に飾る棚)
・ 提灯やお供え物の用意
・ 参加者(親族や親しい方)への案内
地域によっては、お寺様が棚経としてお経をあげに回るところもあります。家族だけで静かにおこなうケースも増えており、形式にとらわれすぎず「感謝の気持ち」を込めて準備すれば十分です。
3. 法要の基本スケジュールと内容
葬儀後は、節目ごとに法要が行われます。特に重要なのが以下の2つです。
四十九日法要
・ 故人が成仏するまでの大切な節目。
・ お寺での読経と、お墓への納骨がセットで行われることが多いです。
一周忌法要
・ 亡くなってから1年後に行う供養。
・ 家族・親戚が集まり、読経と会食を行うことが一般的。
いずれも、お寺への相談・日時調整・お布施やお供えの準備などが必要です。家族葬でも、法要は省略せず行うケースが多いため、早めの準備をおすすめします。
4. 家族葬後の供養をスムーズに進めるためのポイント
【お寺と早めに連絡をとっておくこと】
法要やお盆の予定は、直前になると希望日が取れないことも。早めに相談しましょう。
【家族の意見をすり合わせる】
規模や費用の考え方は人によって異なります。無理のない内容で話し合いを。
【形式にとらわれず「心を込める」ことを大切に】
家族葬のよさは、自由さと温かさ。気持ちがこもった供養が一番です。
5. 香典や供養品の準備は必要?
家族葬のあとに行う初盆や法要では、「香典」や「供養品(返礼品)」の準備が必要なのか迷う方も多いです。ごく親しい身内だけで行う場合、香典を「辞退する」「包まない」ことも珍しくありません。
【香典について】
・ 親族内だけで行う場合は香典なしが一般的なケースも。
・ 外部の方を招く場合や、お寺にお経をお願いする場合は用意しておくと安心です。
【供養品・返礼品について】
・ 法要後のお礼として、菓子折りや日用品などの品物を渡すことが多いです。
・ 参加者が少人数であれば、形式にとらわれず「感謝を伝える」気持ちが大切です。
不安な場合は、地域の慣習やお寺に確認しておくと安心です。最近では「簡素に、でも心を込めて」が主流になってきています。
まとめ|家族葬のあとも、心を込めた供養を
家族葬が終わったあとも、供養の時間は続いていきます。初盆や法要は、亡くなった方を想い、ご家族が心を整える大切な節目です。形式にとらわれすぎず、「どうすれば自分たちらしく供養できるか」を軸に考えてみましょう。
不安な場合は、お寺や葬儀社に相談するのも安心です。家族の絆を大切にしながら、ゆっくりと向き合っていけますように。
また、法要やご葬儀に関してわからないことがある方や、準備が難しい方は相賀佛光堂にご相談ください。相賀佛光堂は、玉野市・岡山市南区エリア(旧灘崎町、迫川、荘内、常山、八浜、宇野、築港、直島、豊島)で「地元とともに生きる」葬儀社です。地元で安心して葬儀をあげていただけるよう、まごころを込めてお客様に寄り添いサポートいたします。仏事でお困りの際はお気軽にご相談ください。